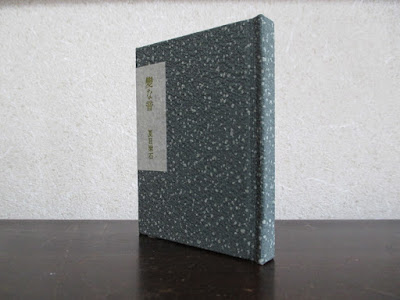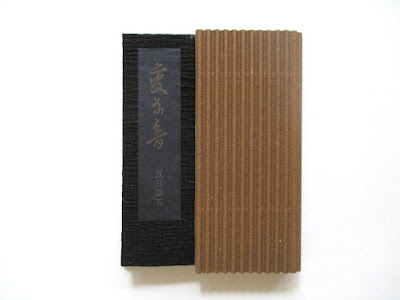日本語も英語もまったくなんちゃって訳です。
こんなことを言いたいのだろう、きっとそうだろうと。
陶淵明 帰去来兮 homeward bound
序 Prologue
私の家は貧乏で、百姓だけでは食べて行けない。
My house being poor, cannot live with just the farmer.
幼い子どもがいつも腹を空かせているが、家には一粒の米もなく、収入を得るめどもない。
The young child has spaced the stomach always, but there is no either food completely in the house and there is no either aim which works.
親戚が私に官吏になれとすすめるが、どうしたらなれるのだろう。
The kindred being accustomed recommends to the official in me, but if how it does, probably will be accustomed to the official.
たまたま皇帝が入れ替わる時だった。
Accidentally when the emperor inserts and substituting was.
窮状を見かねた叔父が官吏の仕事を周旋してくれた。
From combining, the uncle who justified sympathy mediated the work of the official.
世の中はまだ戦乱が続いていたので、遠くへは行けない。
Because as for society disturbances of war were continued still, the distance was dangerous.
勤め先の彭澤(ホウタク)は家から僅か十里ほどの隣町で、公田の収獲で酒をつくることもできるらしい。
The Houtaku of the workplace from the house harvesting the wheat in next door town about of 25 miles, can also make the liquor seems.
わたしは思い切って就職した。
I was employed resigning.
しかし勤めて二か月あまり、日に日に故郷への思いが強くなる。
But serving, two month remainders, in day the thinking to the home becomes strong in day.
人の性格は無理に歪めたり誤摩化したりはできないものだ。
It is something where character of the person does not twist unreasonably and it is not possible, and does not cheat in the same way and is not possible.
貧乏はもちろんつらいが自分の気持に嘘をつく毎日も同じようにつらい。
Poverty of course balance. But every day when lie you are attached to your own feeling in the same way balance.
本来の自分の意思とかけ離れた世界にいることを恥ずかしく思う。
Being in the world where I think shy, am widely different with original my own intention.
秋の収穫が終わったらいさぎよく辞めようとわたしは心に決めた。
I decided in heart, being fall, when harvest of the wheat ends, that it will stop.
そんなとき遠くへ嫁いだ妹の訃報が届く。もう一刻もこうしては居られない。
That such a time the younger sister who marries to the distance died, the letter reaches. Already, in this way also moment, it cannot stay.
妹の葬儀に参列することを理由に職を辞した。
Attending the funeral of the younger sister job was left in the reason.
中秋から冬まで八十日余り、自らの心の内を「帰去来兮」と題す。
From middle fall to winter a little more than 80 day, among hearts of self “帰去来兮” with entitling.
晋安帝義煕元年十一月
November of 405
(次回に続く)It continues